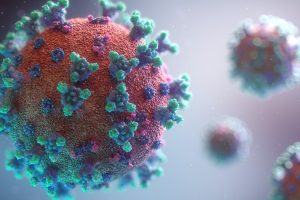<連載第10回>
漢方が「得意」な領域
前回は漢方における急性発熱性疾患の捉え方とその治療方法について取り上げました。
とはいえ、現代日本において「漢方を使うのがよい」とされるのは、おそらくご存知のとおり、“感染症の急性期”などの「因果がはっきりしているもの」ではありません。症状の在り方や対処の方法が西洋医学でははっきりしない、あるいは西洋医学において使用する医薬品があっても「望む治療効果にたどり着くのに困難が伴うケースが多い、副反応などのリスクがある」等の理由から西洋医学のみの治療に不具合が生じる治療領域が、やはり漢方の「得意な領域」となりがちです。
要するに「疾患像が曖昧になりやすい領域」というわけですが――これはそのまま「疾患像をひとことで示すことが困難で、他人に状況を説明しようとすると“ものがたり的になりやすい”領域」、とも言えるのではないでしょうか。
そういった治療領域のひとつである婦人科の、漢方における疾患像の捉え方や治療方法について今回は述べてゆきたいと思います。
婦人科疾患の中でも多くの女性が悩まされるのが、月経(や、生殖)に関連する不定愁訴――これを疾患というのは適切でないかもしれませんが――です。
不定愁訴というのは、不調を感じておりそれを訴える(愁訴)のだけれども、その症状が安定しない――出たり引っ込んだり強度や種類が変わったりする――つまり「不定」である状態を言うので、正確には疾患名ではありません。とらえどころはないけれども、体調が万全でないという事実は明確に存在するという「状態」なのです。
これらは漢方で、生命活動の三要素である「気(き)・血(けつ)・水(すい)」の中でも「血」の不調として捉えられており、「血の道症(ちのみちしょう)」とも総称されます(このときばかりは「ち」と読みますが、それ以外は非常に読みづらいですが「けつ」と読んでください。さもないと“解剖学的な血液”と区別がつかなくなってきますので)。
「血」の不調

さて、この「血」の不調ですが、大別して二種類が存在します。「血虚(けっきょ)」と「血瘀(けつお)」です。血瘀については「瘀血(おけつ)」という表現の方が多く使用されているかもしれません(「瘀血」が症状の完成した状態を指し、その前駆症状を「血瘀」と呼ぶのであるとする説もあります)。
血虚とは文字通り血が虚である――つまり血の総量が足りない、あるいは血の働きが不十分であることを指します。西洋医学でいうところの貧血に近い状態を指しますが、もっと感覚的に“血――この場合は本人の主観的な感覚ですから“ち”と読んでもよいでしょう――が足りていないと感じられる”状態を指す、とも言えます。
血は全身を巡って温め、栄養する働きを持つとされます。ですので、それが不十分であるイメージに結びつく状態――顔色が青白い、皮膚や髪の毛がかさつく、身体に冷えを感じやすい、身体のどこか(多くの場合、頭)から血(ち)が引いていく感覚がある…等のベースがありつつ、月経等に関連して不快な症状が生じる場合は「血虚が原因で色々とまずいことが生じているので、血を補うための薬を使う」となります。
もちろん上記の状態が強く頻回に出現する場合にも、それ以外の症状を伴わないとしても生活に支障を生じているのであれば血虚として血を補う治療を行ないます。
血瘀または瘀血はその逆で、血の気が多すぎる――のではなく、血の巡りが滞っている状態を指します。「瘀」は「停滞する」という意味を持つ字です。
こう言うと、ひところ流行った「血液がドロドロになっている」などという状態と考えられる方もいらっしゃるかもしれません。実際に漢方的に瘀血と診断された人の血液の流れやすさを調べる研究などもなされているのですが、血液の実際の粘度がどうこうというよりは、血の滞り感が目に見えたり体感としてイメージできたりする状態である、というほうが今のところ取りこぼしはないでしょう。例えば舌下静脈の怒張、赤黒い顔色、下腹部を押したときに何かが滞って痛む感じがし、特に月経直前に悪化する…等々(なお、下腹部の圧痛については別の疾患である場合もあるため、本稿を読んでご自身のお腹を押してみることだけで判断するのはやめてください。体感とイメージを結びつける一例としてご紹介しています)。少し意外なところでは、痣なども瘀血の表れと考えられます。血管から漏出した血が散らずにそこに滞っているというわけです。
瘀血の場合には、血虚よりももう少し様々な要素が絡んできます。
なぜ滞ってしまったのか。巡りを促す力が不十分なのかもしれません。巡りをせき止めるような器質的なトラブル(脈管の詰まりなど)があるのかもしれません(例によって脈管は解剖学的な血管とは似ていながらも異なりますが)。血に熱が絡んで水分を飛ばしてしまうことで、血がねばつくようになっているのかもしれません…個々の患者さんの訴えを聞きながら、血の詰まりを改善できる処方を選んでいくことになります。
例えば気剤(きざい)と呼ばれる“気の発散を促す”生薬を用いることで気の巡りの勢いをつけ、血を巻き込んで動かしていく、脈管を緩める作用を持つ生薬を使用する、あるいは血に絡んだ熱を冷ます生薬を用いる…
これらの“作用”はいずれも体感や症状の軽減のされかたからのイメージであり、天然物化学的に解析した場合の成分やその西洋医学的な薬理作用とは異なることもあるのですが、体感に密着しているがゆえに非常に納得しやすくもあるのです。
不定愁訴への対応
婦人科で訴えられがちな不定愁訴への対応については、まずは非常に大ざっぱに3つに分けられます。
ひとつは体力がそもそもあまりなく、冷えや弱々しさを感じやすいひとへの対応。つまり血虚が不調の根源にあるひとへの対応です。
ふたつめは、体力は中等度からやや虚弱に傾きがちで、不快な症状がそれこそ日によってあるいは時間によっても違って感じられるひとへの対応。これは血虚と瘀血が混在するような状況への対応ともいえます。
みっつめは赤ら顔でのぼせやすい傾向があるひとへの対応。瘀血への対応となります。
もちろんこれだけではあまりに大ざっぱすぎるので、体調や症状をより詳しく聞きながら治療計画を立てていくことになるわけです。
「相性がいい」からこそ、注意深く
「こういった体調不良にはこの処方」ということを言いたいわけではないので、処方名も生薬名も本稿では提示しません。
西洋医学的に病因や病巣を見つけ出して取り去っても身体に感じる不調が取り除けない場合に「ものがたりの医学」が手段として残されていること、そして漢方は不調のものがたりをどのように解釈し、どのように対処しているのかということについて、イメージを持っていただくことが本稿の目的です。
そしてもうひとつ――病像の表現が「ものがたること」とあまりに相性がいいがために、本稿で述べたような愁訴を始めとして、種々の婦人科疾患や不調は「西洋医学的な対処を否定する、ものがたり的な解釈や対応を信じ込みすぎる」傾向がある、ということにも留意していただきたいのです。積み重なったイメージはいかに確からしく実感できても、やはりイメージであって実物ではない、ということもあるのですから。