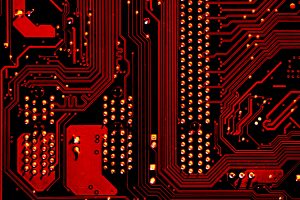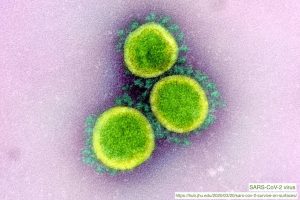<連載第5回>
「語りつくせない」ことが前提
ものがたりの医学を研究することについて。
前回は比較的小さいサイズの“ものがたり”に、現代科学で切り込む場合について述べました。今回はいよいよ、「神話」級の“ものがたり”に現代科学のメス――そう、ブルドーザーでもシャベルでもなく、間違いなくメスなのです――を構えて分け入るケースについて考えていきます。
神話級のものがたりは本当にそれでひとつの世界を成し得ています。世界の成り立ちを説き、生命の仕組みを説き、人の身体の有り様を説き、病と治療法までを語り起こしていきます。
このままでは話が大きくなりすぎるので、少し縮めて具体的な感覚に落とし込んでみましょう。――広大で深い森を想像してみてください。どこに何があるかをひとつひとつ説明することは非常に困難です(できないとはいいません)。分け入ることができず、そこがどうなっているのかわからない場所もあるでしょう(いつか入れるかもしれませんが)。しかし、あいまいな部分を残しながらも森の物語を語ることは可能です。木の葉の1枚1枚について説明しなくても森の概観を伝えることはできるでしょう――というよりも、木の葉の1枚1枚を知ることに諸々を費やしていたら、ついに森の全貌を知ることはできない、というのが本当のところでしょう。
「神話」級のものがたりの医学は、そんな存在です。人体と健康と病と治療法、という名の巨大な森が、語りつくされないまま目の前にあり、語りつくせないことを前提に森の歩き方を説いていくものなのです。“語り尽くせない”をもう少し別の角度から言い換えた言葉がすなわち“全人的”“ホリスティック”もう少し捻ると“心身一如”…などということになります(乱暴でしょうか。でも、そういう言葉で説かれることで、実感を伴わないまま納得してしまっていませんか?)。
なんだ、いい加減なものだな、と思われたでしょうか。
いえ、それこそが「神話」級の医学の強みなのです。
というのも、現代科学は「あいまいだったものを明らかにできる」けれど「わかっていることしかわからない」ものだからです。

「証拠」を待てないこともある
現代科学によって生み出された「証拠の医学」は、いかなる文化圏の人とでもその“証拠”の共有ができるということを前提として発展してきたため、すさまじい勢いで知見を集積し、人体や病の仕組みを解き明かし、治療法を定めてきました。誰でもその“証拠”を理解できる、だれでもその“証拠”の堆積に、自分の見つけ出した新たな“証拠”をさらに積むことができるという前提のもとに「証拠の医学」は構築されてゆき、200年もしないうちに医療のスタンダードとなりました。
でも、全能ではありません。人体や病という“森”は広大なので、木の葉1枚1枚であろうともその存在について証拠を提出しない限り認められない「証拠の医学」の方法では語り尽くせないのです。
そもそも、木の葉について詳しく語っても、森を語ったことにはなりません。そして「証拠の医学」においては、その証拠が提出されていない部分については「証拠がない」ということこそ誠実なので――わからないものは存在しないか、ブラックボックスか、今後解明されるはずだが今は言及できないか、ともあれそういった言葉で言い表されます。
もちろん、科学であれば、それでいい。むしろ、そうでなくては困ります。証拠を積み上げる、というのがルールですから。
でも、医学であれば――わからない、といって放置されてしまっては、今、身体に不都合を抱えている人は困ってしまいます。だからこそ、「ものがたりの医学」が必要とされるのです。
“ものがたり”の「翻訳」は「格闘」でもある
が、ここで大きな問題があります。
「ものがたりの医学」はそれが語り起こされた文化圏と非常に親和性が高い、いわば“土着”の存在です。土地や文化や歴史にしっかりと根を下ろしているものなのです。となると、その文化圏から遠い場所にいる人にそのまま適用しようとすると「なんだかわけのわからない治療」を「いいから試してみよう」とやみくもに実行する…ということにもなりかねません。「いいから信じなさい」といわれて信じられればいいけれど、そうでない場合――これでは治療を受ける側としては非常に不安です。同じ治療を受けるなら、理解できる、あるいは腑に落ちる治療を受けたいと思うでしょう。理解できなければ治療に同意もできません。
手術などと違い、伝統医薬の服薬や伝統医学にのっとった養生法などは、実のところ「まぁ、悪いことはおきないだろう、一応信じておこう」くらいのスタンスで行なっている人も多いのではないでしょうか。これは決していい状態ではありません。異文化圏の“ものがたり”の、共通言語への翻訳は、やはり必要となります。医学の共通言語とは――そう、すなわちいかなる文化圏であっても事実は事実、証拠は証拠、という前提のもとに発達した「証拠の医学」です。
「神話」級医学の“研究”は、ある言語をもうひとつの言語で翻訳するようなものです。文化圏同士の交流、もっと言えば格闘とも言えるでしょう。
「ものがたりの医学」には極端な粗密があり、一方の「証拠の医学」にはまだ証拠が提出されていないがゆえの空白の部分がある中で、「証拠の医学」の言語で「ものがたりの医学」を翻訳しようとしたり、あるいは平気で不条理劇さながらの展開を提示してくる“ものがたり”を“証拠”によって組み上げられた論理で分かりやすく語りなおそうとしたりする行為――これこそが、具体的に言えば、漢方医学やアーユルヴェーダなど、システムとして成立している伝統医学の研究なのです。
「証拠の医学」の語彙が足りず、中途半端な翻訳となることもあるでしょう。例えば「葛根湯が風邪に効く」ことの作用機序ひとつとっても、西洋医学で完全に説明できてはいないのです。
そもそも「証拠の医学」については、新たな“証拠”が見つかったとたん、これまでのシステムががらりと書き換わったりすることもあり(「証拠の医学」はそもそもそういうものです。それどころか、森の木の葉1枚1枚をしらみつぶしに語らずとも森を理解するために、これまでの細かい知見の集積をひっくり返してひとことでまとめられるような真理がどこかにあるのではないか、自分こそがその真理に到達したい――というのが科学者の野望でもあるのです)、そうなったら今までの翻訳や語りなおしの成果がフイになることもあるでしょう。
だからといって“ものがたり”はそのままで完成しているのだから研究は必要ないなどと言ってはいけないし、研究によって解き明かされた“ものがたり”だけが信用できるなどと言ってもいけないのです。――そんなふうに切り捨ててしまうのは、端的に言えば、損です。
今あるものを両方の手で持ちながら、より良い理解と納得、快適さを目指すこと。「神話」級のものがたりの医学の研究は、そのようなものだと受け止めておくのが一番良いのではないかと考えています。
ふたつの医学は並び立って存在し、その二つが格闘じみた交流を続けてゆくことで、私たちは少しずつ理解や納得を深めながら、快適に過ごす手段をより多く手に入れてゆくことになるのですから。