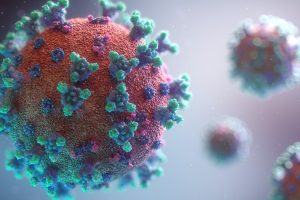<連載第12回>
身体そのものは変わらない
前回は「気の不調」というものがたりについて述べ、また、それに対して用いる漢方処方が持ちうる物質的なバックグラウンドについても少し触れました。
ものがたりは「現象を解釈し、対処方法を導く」ための非常に有効な手段ですが、物質を身体に影響させるという行為がどこかに存在するのであれば、身体はそれこそ“フィジカル(物理的、身体的)に”その行為に対して反応し、それが心身の不調の解決へとつながっていく――というのが、ひとまずはニュートラルなものの見方ではないでしょうか。
「ものがたりの医学」で解釈するにしろ、「証拠の医学」で解説するにしろ、その対象となる身体そのものの存在は変わらないのです。
今回は、その一例として「ものがたりの文脈の中で使用されていたものが、そのあまりの“明確な有用性”から西洋医学の文脈の中で行なう治療のプロトコルに採用された」処方についてご紹介いたします。
大建中湯と開腹手術
大建中湯(だいけんちゅうとう)という処方があります。初出は漢方三大古典のうちの『傷寒雑病論(しょうかんざつびょうろん)』中、慢性病について記した『金匱要略(きんきようりゃく)』で、数ある漢方処方の中でも最もプリミティブな部類に入ります。
人参(にんじん、いわゆる薬用人参)、蜀椒(しょくしょう、本来は中国に産する花椒を指すが山椒も可)、乾姜(かんきょう、生姜を蒸すなどして一度加熱した後に乾燥させたもの)を合わせて煎じた煎じ液に膠飴(こうい、麦芽糖の飴)を煮溶かして作る処方です。ただし、現行の医療用エキス製剤には膠飴は入っていません。

この処方について原典ではこのように記されています。曰く――
心胸中大寒痛嘔不能飮食腹中寒上衝皮起出見有頭足上下痛而不可觸近大建中湯主之(金匱要略・腹滿寒疝宿食病篇)
胸の中が大いに冷えて痛み、嘔吐して飲食ができず、腹の中が冷え、膨満感があり、時には腹壁越しに頭のような丸い形や足のような長い形の膨らみを認める。胸部や腹部に触れようとすると痛がって触らせない。これは大建中湯で治療すべき状態である(注1)。
大建中湯の“中”とは身体の中心を支える腹部を指します。処方名が意味するのは、これはお腹の中の臓器を“大々的に建て直す”ためのものである、ということです。一般的には腹部に冷えを感じていて比較的強い腹痛があり、膨満感や鼓脹を呈する状態に使用する、とされています。この処方を漢方的に、そして現代の言葉で解釈すると、以下のようになります。
胃腸を中心とした強い冷えに対しては身体の深部を温める乾姜で対応する。胃腸がそれだけ冷えて痛むということは全身が虚脱傾向にあると考えられるので、人参で弱った体を温め力づける。
山椒も熱性の薬であり身体を温めるが、同時に「気を発散させる」働きも持つので、張り詰めた腹部のガスをその勢いで散らす。薬液に膠飴を加えるのは、胃腸が働かず食事から栄養を取ることができないため、煮溶かした飴を薬と一緒に飲み、吸収しやすい形でのカロリー摂取を目的とする。
薬用人参はともかくとして、山椒や乾姜(もとはといえば生姜です)は、確かに医薬品でもありますが、スパイス――つまり食品としてのイメージも重なります。古典の原文では非常に重大な疾患に使うような書き方だけれども、何しろ“白髪三千丈の国の文章”だ、要は身体を冷やしたのがきっかけでお腹が張って痛むような時に使う処方なのだろう――そう思われてしまいそうな処方構成です。
ところがこの処方は現在、開腹手術後のイレウス(腸閉塞)防止のために処方されるのが一般的になっています(もちろんお腹が冷えて痛む場合にも使用します)。
術後のトラブル予防を目的として使用する際、特に主治医や執刀医が漢方について知っている必要はありません。大建中湯の漢方的な意義も処方構成も知られていなくても、これが術後のイレウス予防に有効であるという事実(既に証明されているのです)は知られていて、それゆえに術前術後のケアを含む開腹手術のプロトコル内に大建中湯が組み込まれたのです。
大建中湯に関して論文データベース(注2)を検索しますと、現代医学の文献で大建中湯について記す最も古いものは、1950年に報告された急性虫垂炎兼限局性腹膜炎に関する治験となっています。“患者が痛がって触れさせないような激しい腹痛がある”ことを目標として、大建中湯が使用されたのです。
その後、何報かの症例報告が続きますが、1990年ごろを境目として開腹手術後の癒着性イレウスを大建中湯で治療したという症例報告が相次ぐようになります。
この「術後のイレウス」というのは非常に厄介なものです。消化器にトラブルがあって開腹手術をしたのにその予後が悪くお腹が張ってきて、次第に痛みが強くなってくる。開腹して臓器に物理的に触れ、また閉じる――つまり“いじりまわした”影響で、腸管どうし、あるいは腸管と腹壁が癒着してしまい、その部位で腸管が閉じ、ガスが滞留してしまうのです。
絶食や点滴等で治ることもありますが、鼻腔から腸まで減圧用のチューブを挿入する必要がある場合もあります。程度が酷ければ再手術ということにもなりかねません。だというのに術後のイレウスを確実に回避できる方法はありませんでした。
それなら、漢方薬を使ってみよう
そこで、現時点では有用な手段はないのだから、漢方薬を使ってみようと考える人々が出てきたのです。
――開腹して臓器を外気にさらすのだから“大いに冷え”たことになるのではないか
――触らせないほどの激しい痛みはイレウスの痛み方に相当するのではないか
――皮膚を突き上げるように腹が張ってくるというのは、まさにイレウス発症時の腸管のふくらみを指すのではないか
ということで、大建中湯はイレウスに有効なのではないかと考えて投与したのですが、これが著効を示しました。
個々の症例で確かな手ごたえがあったということで、1992年からは多施設での検討が行われ始めました。
複数の病院で、開腹手術をする患者さんについて、大建中湯を服用した場合と服用しなかった場合の予後を比較したのです。その結果「大建中湯は手術後に出現しうる癒着性イレウスを予防する」ということがわかりました(注3)。これは統計学的には相当程度に高いレベルのエビデンス(証拠)となります。
作用機序は(西洋医学的には)わからなくても、とにかく効くという事実の方は西洋医学的に証明できた――そこから、大建中湯は「証拠のある薬」として開腹手術のプロトコルに組み込まれるようになり、それと前後して「大建中湯を投与することで腸の蠕動運動が促進される、そのため癒着が起こらなくなると考えられる」等の大まかな作用メカニズムに関しても研究され、報告されるようになりました(注4)。
これはかなり珍しい例ではあるのです。ちょうど「打つべき手がなくて困っていた」ところに非常に明確な効果を提供できたことから、大建中湯については「ものがたりの中から現れて証拠を獲得する」ことが可能となりました。
これについては「開腹手術後」という、ある意味極端な条件下で検討を行なったことも幸いしたと考えられます。なにしろ臓器を外気に晒すほどの大きなエピソードを経験しているわけですから、もともとの体質がどうであれ、患者さんたちはこの検討の対象となった時点で、みな虚証の状態に揃っていたとも言えるのです。
ともあれ、どのような文脈の中で成立した医学でも、「人間に施され、その影響が症状の変化として現れる」という点では等しくなります。とすれば、人間の身体の反応を介して「ものがたりの医学」と「証拠の医学」が交差し互いにその内容を資するということも、“当然あるべきこと”なのかもしれません。

- 通常日本では「心胸中大いに寒痛し、嘔して飲食すること能はず、腹中寒し、上衝して皮に起り出であらわれ、頭足上下に有り、痛んで触れ近づくべからざるは大建中湯これをつかさどる」と読み下しますが、中国語圏では「心胸中大寒痛 嘔不能飮食 腹中寒 上衝皮起 出見有頭足 上下痛而不可觸近 大建中湯主之」と分かち書きしています。日本語の読み下しでは「頭足上下に有り」がどういった状態を指すのかわかりづらいのですが、「出見有頭足」の場合、「丸い形の膨らみ(頭)や畝状の膨らみ(足)が確認できる」と解釈でき、おそらくこれは腸内にガスが溜まって膨らんだものが腹壁越しに確認できるものを記述したのではないかと考えられます。本稿では大建中湯のイレウスへの有用性を取り上げていることもあり、本文中に示すような解釈といたしました。
- 今回はCiNii(NII学術情報ナビゲータ)を使用
- 杉山貢: 術後癒着性イレウスに対する大建中湯の効果-多施設による検討. Prog Med 12: 1668-1672, 1992など
- 古川良幸ら:Effect of Chinese Herbal Medicine on Gastrointestinal Motility and Bowel Obstruction. 日本消化器外科学会雑誌 28(4), 956-960, 1995 など